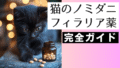現役ペットショップ店長、のあちです。
「あれ?うちのワンコ、なんだか最近臭う気がする…」と感じたことはありませんか?
大好きな愛犬だからこそ、お部屋のニオイや体の臭いはしっかりケアしてあげたいですよね。でも、芳香剤でごまかすのはワンちゃんの鼻にも良くないし、根本的な解決になりません。
実は、犬のニオイには「場所別の原因」があります。そこさえ押さえれば、驚くほどスッキリ解消できるんですよ!
今回は、お店でよく受けるご相談をもとに、ニオイの正体から「今日からお家でできるプロの対策法」、そして私が実際に使って感動した消臭グッズまで一挙にご紹介します。
犬が臭う主な原因
ペットショップの現場でも、多くのお客様からニオイのご相談を受けますが、まずは「どこから」「どんな」ニオイがしているかを見極めるのが、対策への最短ルートです。

体臭
ワンちゃんの体臭と聞くと、私たちはつい「汗のにおい」をイメージしてしまいますが、実は少し違います。
犬の全身には「アポクリン腺」という、タンパク質や脂質をたっぷり含んだベタつきやすい汗を出す汗腺があります。
この汗と、皮膚を守るために分泌される「皮脂」が混ざり合い、空気に触れて酸化したり、皮膚に住んでいる常在菌がそれらを分解したりすることで、あの独特な「獣臭」が発生するんです。
ペットショップの現場で多くの子と接していても感じますが、このニオイの強さは犬種や体質によって本当に千差万別です。例えば、パグやフレンチブルドッグのように顔や体に「シワ」がある子は、その隙間に皮脂や汚れが溜まりやすく、ニオイの温床になりがちです。
ペットショップ店長として特にお伝えしたいのが、この体臭はワンちゃんの体だけでなく、家の中のカーテンやソファといった「布製品」にどんどん移っていくという点です。
一度お部屋にニオイが染み付いてしまうと、後から消すのは至難の業になります。
だからこそ、ワンちゃんの体自体を清潔に保つことは、愛犬のためだけでなく、飼い主さんが毎日を心地よく過ごすためにも、実は一番大切な「お部屋の防臭対策」になるんですよ。

ココがポイント!
・ニオイの犯人は「皮脂の酸化」と「菌の分解」
汗そのものよりも、時間が経って変化した汚れが原因です。
・犬種ごとにニオイの「溜まる場所」が違う
シワの間、指の間、耳の付け根など、空気の通りにくい場所を意識してケアしましょう。
・部屋への二次被害を防ぐ
体臭ケアをサボると、家具や壁紙にまでニオイが移ってしまうので早めの対策が肝心です!
口臭
愛犬がペロペロと甘えてきたときや、顔が近づいたときに「ちょっとお口が臭うかも…」と感じることはありませんか?
犬の口臭の最大の原因は、口の中に残った食べかすが「歯垢(しこう)」となり、そこに細菌が繁殖することにあります。
驚くことに、ワンちゃんの歯垢は人間よりもずっと早く、わずか3〜5日でカチカチの「歯石」に変わってしまいます。
一度歯石になってしまうと、もう家庭での歯磨きでは取ることができず、動物病院で麻酔をかけて処置してもらうしかありません。
ペットショップでも「歯磨きが苦手で…」というご相談をよく受けますが、この歯石を放置して歯周病が進行すると、心臓や腎臓などの健康にまで影響を及ぼすことがあります。
また、意外と見落としがちなのが「胃腸の不調」です。特に食生活が乱れていたり、消化が苦手なものを食べていたりすると、胃の中から上がってくるニオイが口臭として現れることもあります。

ココがポイント!
・「3日の放置」で歯石になる
歯垢が歯石に変わるスピードは人間より早いです。毎日の数分が将来の健康を守ります。
・ニオイで健康がわかる
いつもと違う「生臭さ」や「酸っぱいニオイ」を感じたら、お口のトラブルや内臓の不調を疑ってみましょう。
・「噛むおもちゃ」だけでは不十分
おやつや玩具も効果的ですが、根本的な解決にはやはり歯磨きが一番です!

こちらの記事もご覧ください♬
耳のニオイ
愛犬を撫でているときに、ふと耳のあたりから「ツンとするニオイ」や「酸っぱいニオイ」を感じたことはありませんか?
実は、耳はワンちゃんの体の中でもトップクラスにトラブルが起きやすく、ニオイが出やすい場所なんです。
犬の耳の中は人間と違って「L字型」に急カーブしているため、非常に通気性が悪く、湿気や汚れが溜まりやすい構造になっています。
特に「たれ耳」の子は、耳の穴に蓋をされているような状態なので、さらに蒸れやすくなります。このジメジメした環境で、細菌やカビの一種(マラセチア菌など)が増殖してしまうと、独特の強いニオイを放つようになります。
ペットショップの現場でも、「最近、耳をずっと振っている」「足で耳を頻繁に書いている」という変化に気づいた飼い主さんに耳をチェックしてもらうと、中で炎症が起きていて強いニオイが漂っていることがよくあります。
シャンプーの時に耳の中に水が入ったままになっていたり、湿気の多い梅雨時期などは特に注意が必要です。

ココがポイント!
・「たれ耳」と「毛」が要注意
耳が垂れている子や、耳の中に毛が生える犬種は特に蒸れやすいので、こまめなチェックが必須です。
・ニオイの種類に注目
正常な耳垢のニオイとは違う「酸っぱい」「生臭い」と感じる時は、外耳炎などのトラブルが起きている可能性が高いです。
・シャンプー後の乾燥を忘れずに
耳に水分が残ると一気に菌が繁殖します。洗った後はしっかり乾燥させてあげましょう。
排泄物のニオイ
愛犬との暮らしで、避けて通れないのが排泄物のニオイの問題ですよね。
おしっこやうんちのニオイが家の中にこもってしまうと、飼い主さんはもちろん、遊びに来たお客様に「犬臭い」と思われないかヒヤヒヤしてしまう…というお悩みも、ペットショップで本当によく伺います。
実は、排泄物のニオイの強さは、その子の「腸内環境」や「食べているフード」に大きく左右されます。例えば、タンパク質の質が合っていなかったり、添加物が多い食事をしていたりすると、腸内で悪玉菌が増えて、うんちのニオイが強烈になることがあります。
また、おしっこについても、水分不足で尿が濃くなるとアンモニア臭がキツくなります。店長として多くのお客様のアドバイスをしてきましたが、「フードを変えたら、部屋のニオイが気にならなくなった!」というケースは意外と多いです。
また、ニオイが消えないもう一つの原因は「排泄後の処理」にあります。
トイレシートの吸水性が低くて足裏におしっこがついたまま歩き回ったり、ゴミ箱からニオイが漏れていたりすると、お部屋全体にニオイが広がってしまいます。
臭い対策【今日からできること】と【おすすめ最強アイテム】
ブラッシング
シャンプーよりも手軽で効果的なのが、毎日のブラッシングです。
抜け毛を放置すると、そこで雑菌が繁殖して「獣臭」の原因になります。ブラシで空気を通してあげるだけで、皮膚の通気性が良くなり、ニオイがこもりにくくなります。

ココがポイント!
散歩帰りにサッとブラッシングするだけでも、外でついたホコリや花粉、汚れが落ちて、お部屋にニオイを持ち込まずに済みます。
皮膚を傷つけず抜け毛がごっそり!「ZOORO(ゾーロ)」
短毛種のニオイ対策に革命を起こすのが、このZOORO(ゾーロ)です。
独自の波状ブレードが、皮膚を傷つけることなく不要な抜け毛やフケを驚くほどごっそり取り除きます。
刃に毛が絡まないので、お手入れの手間も一切なし。人間工学に基づいた形状で、愛犬も痛みを感じにくいため、ブラッシングが苦手な子にも最適です。
短毛種オーナーなら一本は持っておきたい、イチオシの「一生モノ」のコームです。
歯みがき
口臭対策の基本はやはり歯磨きですが、嫌がる子も多いです。
まずは指にガーゼを巻いて拭くだけでもOK。大切なのは、歯垢が歯石に変わる前に「物理的に汚れを落とす」ことです。

ココがポイント!
最近は、舐めるだけで汚れを浮かすジェルや、噛むだけでケアできる高機能なおやつも増えています。愛犬のストレスにならない方法から始めてみましょう。
舐めるだけで汚れを浮かせるブレスワン
歯磨き嫌いのワンちゃんにこそ試してほしいのが、このブレスワンです。
舐めるだけで歯垢を浮かせ、お口のニオイを元からケアしてくれるデンタルジェルと、使いやすい専用グッズがセットになっています。
美味しい味でワンちゃんも喜んで受け入れてくれるため、格闘することなく日々のケアが習慣になります。
シャンプー
ニオイの元となる酸化した皮脂を、根本から洗い流すのがシャンプーの役割です。
ただし、洗いすぎは逆に皮脂の過剰分泌を招くので、月に1〜2回、質の良いシャンプーで行うのがベスト!

ココがポイント!
シャンプー選びのコツは、香料でごまかさず「ニオイの原因菌」にアプローチできるものを選ぶこと。
また、指の間の水気をしっかり乾かすことが、後からの「生乾き臭」を防ぐ最大の秘訣です。
【サロンの香り】皮脂汚れをスッキリ落とす「A.P.D.C. ティーツリーシャンプー」
ニオイ対策シャンプーの決定版といえば、このA.P.D.C.です。
消臭・清浄効果の高いティーツリーなど、6つの植物成分がベタつく皮脂汚れを根こそぎ落とし、気になる「獣臭」をスッキリ解消。
爽やかなハーブの香りが驚くほど長持ちし、自宅でサロン帰りのような仕上がりが楽しめます。
泡切れも良く、保湿成分もたっぷり配合されているので、私としても「迷ったらこれ!」と太鼓判を押す、安心・安全な一本です。
耳掃除
たれ耳の子や、耳毛の多い子にとって、イヤークリーナーでのケアは必須です。
綿棒で奥までこするのはNGですが、専用の洗浄液を使って耳をクチュクチュと揉むだけで、驚くほど汚れとニオイがスッキリします。

ココがポイント!
耳のニオイが気になり始めたら、まずは洗浄液で「浮かせて取る」ケアをしましょう。
耳の中を常にサラサラに保つことが、外耳炎の予防にも繋がります。
【耳のニオイを元から断つ】プロも愛用する定番ケア「ノルバサンオチック」
耳のニオイ対策に欠かせないのが、世界中で愛されるノルバサンオチックです。
洗浄液を耳に入れて揉むだけで、奥に溜まった汚れを優しく浮かせて除去。殺菌成分がニオイの原因菌に直接アプローチし、外耳炎などのトラブル予防にも効果を発揮します。
さらっとした使用感で乾きが早く、私としても「最初の一歩」として一番におすすめしたい、信頼のメディカルケアアイテムです。
生活環境を整える
ワンちゃんの体そのものをケアしても、お部屋のニオイが消えない……。そんな時は、家の中にニオイが「蓄積」してしまっている可能性があります。
特にトイレ周りの床や壁、毎日寝転がるソファやカーペットは、目に見えない排泄物の飛び散りや皮脂汚れが染み込み、時間が経つほど強力な「生活臭」へと変わっていきます。
ペットショップ店長としてアドバイスしたいのは、市販の芳香剤でニオイを上書きするのではなく、「菌を元から断つ」という考え方です。
強い香りでごまかしても、ニオイの根本が残っていれば混ざり合って逆効果になることも。また、鼻が良いワンちゃんにとって、強い人工香料はストレスになる場合もあります。

ココがポイント!
「香りでごまかさない」のが鉄則
根本的な原因菌を分解しない限り、ニオイは何度でも復活してしまいます。
目に見えない「蓄積」をなくす
トイレ周辺だけでなく、愛犬がよく顎を乗せている場所や、壁の低い位置も意識して拭き上げましょう。
安全性は何よりも優先
ワンちゃんが舐めてしまう場所だからこそ、アルコールフリーなど低刺激な成分にこだわることが大切です。
ニオイを元から分解!お肌に優しい「ナノコロナチュレ」
お部屋のニオイだけでなく、愛犬の体にも直接使えるナノコロナチュレは、私が自信を持って推す万能スプレーです。
ノンアルコールで肌に優しく、動物病院でも肛門腺の洗浄に使われるほど消臭・除菌力が優秀。お散歩後のケアや、お風呂が難しいシニア犬の体拭きにも最適です。
これ1本で、体臭から排泄臭まで「菌を元から分解」してくれるので、本気でニオイを断ちたい方の強い味方になりますよ。
まとめ
この記事では、愛犬の気になる臭いの原因から、今日からできる具体的な対策までを幅広く解説しました。体臭、口臭、耳、排泄物、生活環境、被毛、そして病気まで、様々な要因が臭いの元となることをご理解いただけたかと思います。
日々のブラッシングやシャンプー、歯磨き、耳掃除といったケアはもちろん、生活環境を清潔に保ち、フードを見直すことも大切です。さらに、この記事でご紹介した消臭スプレーや空気清浄機などの対策グッズを上手に活用することで、より効果的に愛犬の臭い対策を行うことができます。
これらの情報を参考に、あなたと愛犬に合った対策を見つけて、より快適で清潔な毎日を送ってくださいね。もし臭いが改善しない場合は、動物病院への相談も検討しましょう。