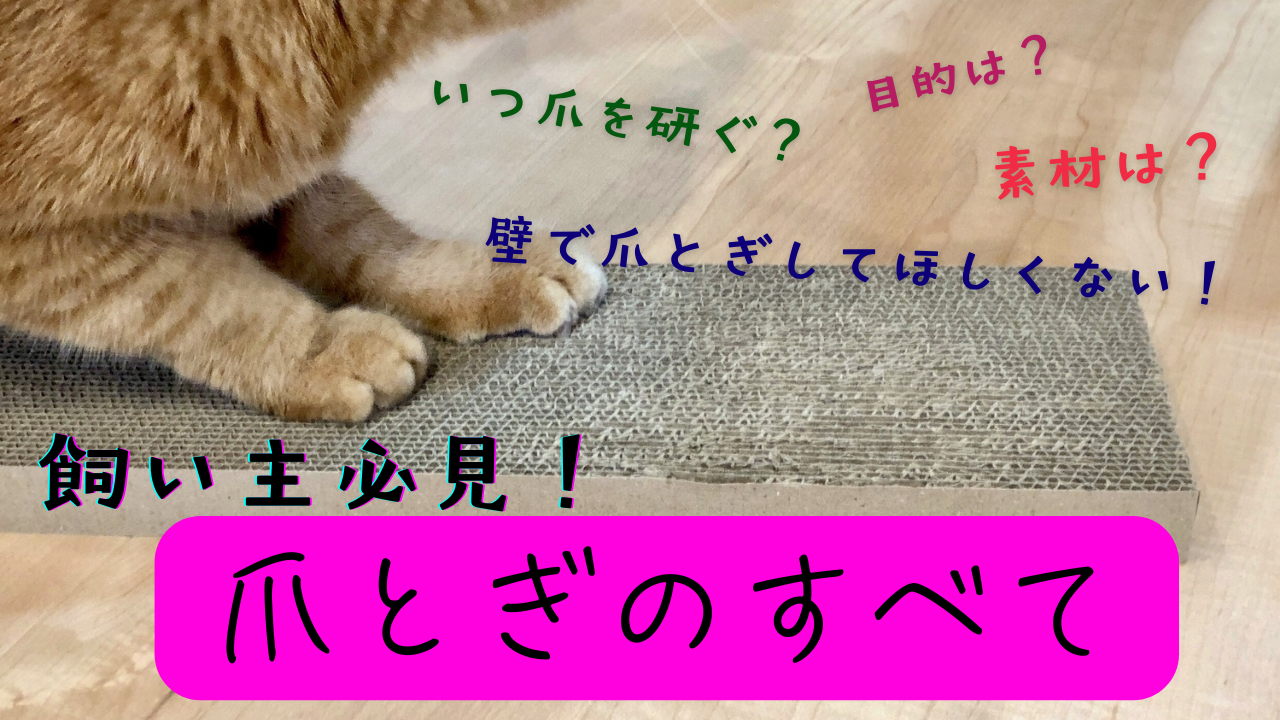現役ペットショップ店長、のあちです。
なぜ猫は爪とぎをするのか、ご存知ですか?ただ単に爪を研いでいるだけだと思っていませんか?
実は、爪とぎには猫にとって大切な意味があるのです。爪の手入れはもちろん、マーキングやストレス解消など、様々な理由が隠されています。もし爪とぎをしないと、猫自身にも悪影響があるかもしれません。
この記事では、猫の健康と快適な暮らしを守るための、猫の爪とぎの理由から、適切な爪とぎの選び方、しつけ方まで、あなたの悩みを解決するヒントをご紹介します。

猫が爪とぎをする理由
猫が爪とぎをする理由は、大きく分けて以下の4つです。それぞれ詳しく解説します。
爪のメンテナンス(お手入れ)
猫の爪は、玉ねぎの皮のように何層にも重なっており、内側の新しい爪が成長するにつれて外側の古い爪が自然と剥がれ落ちる構造になっています。
この古い爪の層を効率的に取り除き、常に鋭い爪を維持するために行われるのが「爪とぎ」です。人間が爪を切る行為と似ており、爪のメンテナンスとして重要な役割を果たしています。
爪とぎは、単に古い爪を剥がすだけでなく、爪が伸びすぎて物に引っかかり、怪我をするのを防ぐ効果もあります。
伸びすぎた爪は日常生活で不便なだけでなく、折れたり剥がれたりする原因となり、猫にとって痛みや不快感をもたらす可能性があります。
マーキング
猫の足裏にある肉球には臭腺という匂いを分泌する器官があり、この匂いを活用したマーキング行動が爪とぎの重要な目的の一つです。
爪とぎを行うことで、臭腺から出る特有の匂いを爪を研いだ場所に擦り付け、他の猫に対して「ここは自分の縄張りだ」と主張します。
これは、視覚的な情報だけでなく、嗅覚的な情報も用いた効果的な縄張り主張の方法と言えるでしょう。
さらに、爪とぎによって残された爪痕自体も、他の猫に対する視覚的なマーキングとして機能します。特に、壁や柱の高い位置で爪とぎをすることで、爪痕はより目立ち、広範囲に自分の存在をアピールする効果があります。
これは、「自分はこんなに大きいんだぞ」と誇示しているかのように、自身の優位性を示す行動とも言えます。
気分転換・ストレッチ
爪とぎは、単なる爪の手入れにとどまらず、猫にとって心身のリフレッシュに繋がる重要な行動です。体を大きく伸ばしながら爪を研ぐことで、気分転換を図っていると考えられています。
特に、寝起きや遊びの後など、体を動かした後に爪とぎをする様子はよく見られ、これは人間でいうストレッチや軽い運動に相当すると言えるでしょう。
この行動は、単に爪を研ぐだけでなく、全身の筋肉を大きく動かすことで、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進する効果も期待できます。
長時間同じ体勢でいた後の体のこわばりを解消したり、遊びで使った筋肉をリラックスさせたりするのに役立っているのです。
ストレス解消
猫は、環境の変化、不安、退屈など、様々な要因からストレスを感じます。
例えば、引っ越しや新しい家族の加入、騒音、留守番などがストレスの原因となることがあります。爪とぎは、こうしたストレスを解消するための重要な行動の一つです。
爪とぎに集中することで、猫は一時的にストレスの原因から意識をそらし、精神的な安定を取り戻そうとします。これは、人間が集中して何かに取り組むことで嫌なことを忘れられるのと似ています。
爪を研ぐという行為に没頭することで、不安や緊張を和らげ、心を落ち着かせることができるのです。
爪とぎを使わないとどうなる?
猫が爪とぎを使わないと、飼い主と猫の双方に様々な問題が生じる可能性があります。具体的に見ていきましょう。
飼い主側の問題
- 家具や壁の損傷:猫が爪とぎをしない場合、代わりに家具(ソファー、柱、壁など)で爪を研ぐ可能性が高まります。
- 掃除の手間:爪とぎは古い爪の外側の層を剥がす行為なので、どうしても研ぎカスが出ます。適切な場所で爪とぎをしてくれれば掃除も比較的楽ですが、あちこちで爪とぎをされると掃除の手間が増えてしまいます。
- 精神的なストレス:家具の損傷は飼い主にとって大きなストレスとなります。「またやられた…」という気持ちが積み重なると、猫との生活が楽しめなくなってしまう可能性もあります。
猫側の問題
- 爪の異常:古い爪が剥がれずに伸び続けると、爪が内側に巻き込む「巻き爪」になることがあります。これは痛みや不快感、歩行困難、化膿の原因となります。また、爪とぎ不足は爪の変形にも繋がります。
- ストレスの蓄積:猫にとって爪とぎは重要なストレス解消行動です。爪とぎができない環境では、ストレスが蓄積し、様々な問題行動を引き起こす可能性があります。
- 運動不足:爪とぎは、猫にとって体を伸ばすストレッチのような効果があり、運動不足解消にも繋がります。爪とぎをしないと運動不足になり、肥満や運動能力の低下を招く恐れがあります。
爪とぎをするタイミング
猫が爪とぎをするタイミングは、いくつかのパターンがあります。猫の行動をよく観察することで、その理由や気持ちが見えてくるかもしれません。以下に代表的なタイミングとその理由をまとめました。
起床後すぐ
理由・・・
寝ている間に固まっていた筋肉を伸ばしたり、血行を促進したりするため、起床後すぐに爪とぎをします。
人間でいうストレッチのようなもので、体を大きく伸ばしながら爪とぎをする様子はよく見られます。
様子・・・
背伸びをするように体を伸ばし、前足を交互に動かしながら爪とぎをします。
食事のあと
理由・・・
食事でエネルギーを摂取した後、気分転換や満足感を得るために爪とぎをすることがあります。
様子・・・
食事の後、落ち着いた様子でゆっくりと爪とぎをすることが多いです。
遊びの前や後
理由・・・
遊びの前は、これから活動するための準備運動として、遊びの後は興奮を鎮めたり、気分を切り替えたりするために爪とぎをすることがあります。
様子・・・
遊びの前は、やる気に満ちた様子で爪とぎをし、遊びの後は、少し落ち着いた様子で爪とぎをすることが多いです。
飼い主へのアピール
理由・・・
飼い主の注意を惹くために、わざと飼い主の近くで爪とぎをすることがあります。「かまって」「遊んで」というサインかもしれません。
様子・・・
飼い主の視線を感じながら、あるいは飼い主に向かって爪とぎをすることがあります。
正しい爪とぎの設置場所
猫の爪とぎの適切な設置場所は、猫が快適に爪とぎを行い、かつ家具などを傷つけないようにするために非常に重要です。以下のポイントを参考に、愛猫にとって最適な場所を見つけてあげましょう。
猫がよくいる場所や通り道
猫は自分の縄張り(テリトリー)のなかで爪とぎをする習性があります。そのため、爪とぎ器は猫が普段よく過ごす場所に設置するのが効果的です。具体的には、寝床の近く、日向ぼっこをする窓辺、食事場所の近くなどが挙げられます。
これらの場所は猫がリラックスしている状態、もしくは行動の前後に立ち寄りやすい場所であり、自然な流れで爪とぎを利用する可能性が高まります。
また、家の中を移動する際の通り道に設置するのも有効です。例えば、朝起きた後に爪とぎをする習慣がある猫であれば、寝床から出てすぐの場所に爪とぎを設置することで、スムーズに爪とぎをすることが多くなるでしょう。
壁や家具の近く
猫が特定の壁や家具で爪とぎをしてしまう場合の最も効果的な対策は、その場所のすぐ近くに爪とぎを設置することです。これは、猫の行動範囲と好みに合わせた対策と言えます。
壁で爪とぎをする猫には、壁掛けタイプやコーナータイプの爪とぎが適しており、家具で爪とぎをする猫には、家具の脚に巻き付けるタイプの爪とぎなどが効果的です。
既に傷つけられてしまった場所には、保護シートなどを貼って補修し、その上から爪とぎを設置することで、再び同じ場所で爪とぎをされるのを効果的に防ぐことができます。
これは、猫に「ここで爪とぎをして良い」と教えるとともに、物理的に傷つけられないようにする二重の対策となります。
出入口や窓際
猫は出入り口や窓際など、外の様子が見える場所で爪とぎをする行動が見られます。これは、外の世界に向けて自分の存在をアピールする、つまりマーキングの一環と考えられています。
外の匂いや音、他の動物の気配などを感じ取ることで、縄張り意識が高まり、爪とぎによって自分の匂いを付着させようとするのです。
このような猫の習性を利用し、玄関や窓の近くに爪とぎを設置することは、これらの場所での爪とぎを防ぐと同時に、猫のマーキング欲求を満たす効果的な対策となります。
複数の種類を複数の場所に
猫はそれぞれ爪とぎをする場所の好み、例えば素材(ダンボール、麻、木など)、形状(縦型、横型、斜め型など)、角度などに個体差があります。
そのため、一つの場所に一つの爪とぎを置くだけでなく、複数の場所に異なる種類の爪とぎを設置することで、猫が最も好む場所や素材を見つけやすくなります。
具体的には、壁に立てかけて使う壁掛けタイプ、床に置いて使う据え置きタイプ、床に敷くマットタイプなど、様々な種類の爪とぎを用意し、猫がどのように反応するかを観察しましょう。
最初は色々な場所に置いてみて、猫がよく使う場所や好む素材が分かってきたら、その場所に集中的に配置すると効果的です。
安定した場所
爪とぎが不安定な場所に設置されていると、猫は安心して爪とぎをすることができません。
グラグラ揺れたり、倒れたりする爪とぎでは、猫は十分に力を入れて爪を研ぐことができず、爪とぎ自体を嫌がるようになってしまう可能性があるため、爪とぎはしっかりと固定された安定した場所に設置することを心がけましょう。
床に置く据え置きタイプの爪とぎを選ぶ場合は、底面に滑り止めが付いているものを選ぶと安定性が高まります。
また、壁に取り付ける壁掛けタイプの爪とぎの場合は、ネジやフックなどでしっかりと壁に固定し、使用中に落下しないように注意が必要です。
爪とぎの使わせ方
猫に爪とぎの正しい使い方を教えるのは、根気と工夫が必要です。
猫は本来、本能的に爪とぎをする動物ですが、人間が用意した爪とぎを好んで使うように促すためには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。
ステップ1:猫が好む爪とぎを用意する
猫の爪とぎ選びでは、素材、形状、大きさが重要です。
素材は猫によって好みが異なり、ダンボール、麻、木、カーペットなど様々な種類があります。最初は複数の素材を試して、愛猫の反応を見るのがおすすめです。どの素材がお気に入りか見極めましょう。
形状も据え置き型、壁掛け型、マット型、ポール型など多岐に渡ります。猫が体を伸ばして爪とぎができる高さで、かつ安定感のあるものを選びましょう。不安定な爪とぎは猫が嫌がる原因になります。
大きさも考慮が必要です。子猫には小さめのもの、成猫には十分に体を伸ばせる大きさのものを選びましょう。小さすぎると十分に爪を研ぐことができません。
このように、素材、形状、大きさを考慮して、愛猫にぴったりの爪とぎを見つけてあげましょう。
ステップ2:爪とぎを適切な場所に設置する
猫がよくいる場所、通り道、壁や家具で爪とぎをしてしまう場所の近くに爪とぎを設置しましょう。
また、複数の場所に異なる種類の爪とぎを置くことで、猫の好みに合った場所や素材を見つけやすくなります。
ステップ3:猫を爪とぎに誘導する
猫に爪とぎを教えるには、猫が爪とぎをしそうなタイミングを見計らって誘導することが重要です。
例えば、起床後、食後、遊びの前や後など、猫が体を伸ばしたり、気分転換をしたくなるタイミングで、爪とぎの場所に優しく連れて行きましょう。
おもちゃやおやつを使うのも効果的な方法です。おもちゃで爪とぎの場所まで誘導したり、爪とぎの近くでおやつを与えることで、「爪とぎ=良いこと」というイメージを植え付けることができます。
また、猫の気を引くアイテムとして「またたび」も有効です。爪とぎに少量擦り付けることで、興味を示し、爪とぎをするように促せます。
さらに、飼い主が実際に爪とぎを使う様子を見せることも、猫にとって良い手本となります。
ステップ4:爪とぎを褒める
猫が爪とぎで爪を研いでいるのを見かけたら、優しく声かけ、撫でたり、おやつを与えたりして褒めましょう。
褒めることで、猫は「ここで爪とぎをすると良いことがある」と学習し、積極的に爪とぎを使うようになります。
ステップ5:間違った場所での爪とぎを阻止する
猫が家具や壁などで爪とぎを始めたら、すぐに中断させることが大切です。
大きな音を立てて驚かせたり、大声で叱ったりするのは逆効果となるため避けましょう。猫はなぜ叱られているのか理解できず、飼い主に対して不信感を抱いてしまう可能性があります。
代わりに、優しく猫を抱き上げて、用意しておいた爪とぎの場所に連れて行き、そこで爪とぎを促してみましょう。
爪とぎ器に興味を示すように、優しく誘導したり、おやつやおもちゃで気を引いたりするのも効果的です。
また、爪とぎをしてほしくない場所には、猫が嫌がるもの、例えば両面テープやアルミホイル、猫よけシートなどを貼っておくのも有効な対策です。
爪とぎの種類と特徴
猫の爪とぎは、素材、形状、設置方法など、様々な種類があります。
それぞれの特徴を理解することで、愛猫に合った爪とぎを見つけることができるでしょう。以下、詳しく解説していきます。
素材による分類
ダンボール
安価で手に入りやすく、猫が爪を引っ掛けやすいのが特徴です。
研ぎカスが出やすいというデメリットもありますが、猫によってはこの研ぎカスを掻き出すのも楽しんでいるようです。
初めて爪とぎを用意する場合や、複数箇所に設置したい場合にオススメです。
安価・入手しやすい・猫が好みやすい
研ぎカスが出やすい・耐久性が低い
麻
耐久性が高く、研ぎカスが出にくいのが特徴です。
硬めの素材で、しっかりと爪を研ぎたい猫に向いています。麻の匂いを嫌う猫もいます。しっかりと爪を研ぎたい猫、掃除の手間を減らしたい場合に向いています。
耐久性が高い・研ぎカスが出にくい
ダンボールより高価・麻の匂いを嫌う猫もいる
カーペット
カーペットや布製の家具で爪とぎをする猫におすすめです。
柔らかい素材で、爪への負担が少ないのが特徴です。布製の家具で爪とぎをする猫や高齢の猫に向いています。
爪への負担が少ない
麻より耐久性が低い
木製
自然な素材で、耐久性が高いのが特徴です。木の質感や匂いを好む猫もいます。
比較的高価で、種類は少ないです。自然な素材を好む猫、長く使える爪とぎを探している場合に有効です。
耐久性が高い
比較的高価・種類が少ない
形状による分類
猫の爪とぎは、形状によって様々な種類があります。
板状(平面型)
最も一般的な形状で、床に置いて使用します。ダンボール製が多く、手軽に入手できるのが特徴です。場所を取らないため、様々な場所に設置しやすいのも利点です。
ポール型(円柱型)
柱に麻縄などを巻き付けた形状で、猫が立って縦に爪とぎをするのに適しています。キャットタワーの一部として組み込まれていることも多く、猫の運動不足解消にも役立ちます。
壁掛け型
壁に取り付けて使用します。壁で爪とぎをする猫におすすめです。壁面を有効活用できるため、場所を取らないのも魅力です。
コーナー型
部屋の角に設置するタイプで、場所を取らずに設置できます。壁際で爪とぎをする猫に最適です。
トンネル型・ハウス型
中に入ってくつろいだり、上で寝たりできる爪とぎです。爪とぎ以外の用途も兼ねているため、猫の居場所の一つとなります。
【店長厳選】素材・形状別!ストレス解消におすすめ爪とぎ3選
爪とぎは、猫の性格や習慣によって「好きな素材」や「好きな形状」が異なります。合わないものだと使ってくれないため、失敗しない選び方が重要です。
ここでは、「耐久性」と「猫の好み」を考慮し、お客様から特に好評な爪とぎをタイプ別に厳選してご紹介します。
【環境に優しい】アレンジ自在!捨てやすいダンボール製爪とぎ&ハウス
多くの猫が好むダンボール素材に特化した、爪とぎと猫用品の専門店です。
最大の魅力は、リサイクル可能で環境に優しい点と、アレンジの自由度があること。爪とぎはもちろん、猫ハウスやおもちゃもダンボール製で、もし猫が使わなくなっても処分が簡単です。
猫の好奇心を満たしつつ、SDGsにも配慮したい飼い主さんに最適。愛猫が気に入るダンボール製品を見つけて、爪とぎの習慣化をサポートしましょう。
【丸型でくつろげる】爪とぎ&ベッド2役!大型猫も安心のXLサイズ
床置き型(据え置き型)で大人気の「バリバリボウル」は、猫の体にフィットするすり鉢状の丸い形状が特徴です。
爪とぎとして使うのはもちろん、そのまま快適なベッドとしても使えます。特にこのXLサイズは、体重6kg超えの大きな猫でものびのびと使える直径48cm。
爪とぎ部分は交換可能で経済的です。
【思いっきり伸びる!】高さ60cmのポール型!麻素材でストレス解消
壁や家具で縦に爪とぎをしてしまう猫には、ポール型(縦型)がおすすめです。
この商品は、猫が心地よく全身を伸ばしてつめとぎができる高さ60cm。リラックスしながら伸びる行動は、幸福ホルモンの放出にも繋がると言われています。
ずっしり重たい台座で安定感も抜群なため、力の強い猫でも倒れる心配がありません。
また、耐久性の高い麻素材は使い込むほど猫好みになり、爪とぎ部分のみ交換可能なのも嬉しいポイントです。
まとめ
猫にとって爪とぎは、単に爪を研ぐだけでなく、心身の健康維持に不可欠な行動です。
爪とぎをしないと、巻き爪などの爪の異常や、ストレスによる問題行動(過剰なグルーミング、攻撃性の増加など)を引き起こす可能性があります。
適切な爪とぎ器を用意し、猫が自由に爪とぎできる環境を整えましょう。素材はダンボール、麻、カーペットなど様々で、形状も据え置き型、壁掛け型、ポール型などがあります。猫の好みや設置場所に合わせて選びましょう。
爪とぎは猫の自然な行動なので、無理に止めさせるのではなく、適切な環境を提供することが、猫と人間が快適に暮らすための秘訣です。

合わせて読んでね♪
爪とぎ兼ベッドの「バリバリボウル」が人気なように、猫にとって安心してくつろげる場所は非常に重要です。
愛猫が最もリラックスできる「最高のベッド」を見つけたい方は、こちらの記事も参考にしてください!